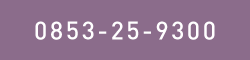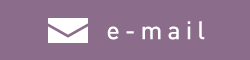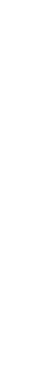暮らしを支える“建築の箱”
2025.08.05
本日8月5日は「箱(はこ)の日」です。「8(は)」「5(こ)」の語呂合わせから、暮らしに欠かせない“箱”に目を向ける記念日とされています🎁
プレゼントの箱や宅配の段ボール、収納ケースなど、箱は身近な存在です。ですが、実は建築の現場にも、たくさんの“箱”があることをご存知でしょうか?
今回は、建築現場で使われる“箱”という言葉や、建物を支える「見えない箱」についてご紹介します。

■現場でよく聞く「箱」
建築や設備の現場では、職人さんたちが「この壁、先に“箱”入れといて」「ここ、“箱抜き”しとく?」など会話を交わすことがあります。
ここで言う「箱」とはスイッチボックスやコンセントボックスなど、電気配線を収納するための小型の金属製・樹脂製の箱をさしています。壁や床の中に設置され、外からは見えなくなりますが、暮らしの快適さや安全性を支える重要な設備です。
これらの“箱”は、壁の仕上げ材を張る前に正確な位置に取り付ける必要があります。少しのズレでも、スイッチやコンセントが使いにくくなったり見た目が悪くなったりしてしまうため、非常に繊細な作業が求められます。
また、配線や配管を通すために、あらかじめ壁や床に穴を設けておく作業を「箱抜き」と呼びます。このスペースがないと、後から配管できず大きな手戻りが発生してしまうため、設計段階から計画される大切な工程です。

さらに、現場では以下のような“箱”も使われています。
●箱金物(はこかなもの)
柱と梁を直角に固定するためのコの字型の金具。構造の補強に使われます。
●箱尺(はこじゃく)
引き出し式(入れ子構造)になっている物差し。狭い場所の寸法を測るのに便利です。

●箱番(はこばん)
工事現場に仮設される小型の作業スペースや事務所。休憩所や資材置き場として使われます。
これらの“箱”は縁の下の力持ちとして施工の現場を支えています💪
■「箱物(はこもの)」という言葉
建築関係者が使う「箱物(はこもの)」という言葉もあります。
これは建物そのものを“ハコ型の構造物”として表現したもので、特に公共施設や大型建築を指すことが多い言い回しです。
たとえば、役所、体育館、美術館、駅舎、ライブハウス、ホールなどが該当します。イベント関係者の間でも「キャパ何人のハコ?」というように、会場を“ハコ”と呼ぶ文化が根づいています。

↑出雲市役所も“ハコ”と呼べます。
一方で「中身より建物ばかりにお金をかけている」という批判的な意味で使われることも💦
ですが現場では「箱物は完成したけど、外構はまだ」「箱物の引き渡しは来週」など、あくまで建物本体そのものを指す言葉として日常的に使われています。
■家具としての「箱物」
「箱物」は、家具の分野でも使われる言葉です。箪笥(たんす)やチェスト、本棚、収納棚など、内部に物をしまう家具全般を「箱物家具」と呼びます。
これに対して、椅子やテーブルのように脚のついた家具は「脚物(あしもの)」と呼ばれています。
収納家具の配置は暮らしやすさを大きく左右する要素です。大きく動かす予定のない箱物家具は設計段階でどこに置くか想定しておくと、より快適な空間を実現することができます。

■建築の中にある、さまざまな“箱”
このように私たちが普段何気なく過ごしている建物の中には、たくさんの「箱」が隠れています。
- 壁の中にあるスイッチボックスやコンセントボックス
- 電気や水道を通すために確保された「箱抜き」スペース
- 安全のための配電盤・分電盤などの箱型設備
- 建物そのもの=「箱物」
ほかにも構造名として使われる“箱”もあります。
たとえば、「箱階段」とは壁で囲まれた箱状の階段室をいいます。「箱庇」は四方を囲われた庇(ひさし)を意味しており、雨風の吹き込みを防ぐ設計上の工夫です。
こうした“箱”を用いた設計・施工が、快適で安全な住環境を生み出しています。

8月5日、「箱の日」。建築の中にある“箱”に注目してみてはいかがでしょうか?
身近な建物や設計の見え方がほんの少し変わるかもしれません☺️

BACK