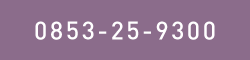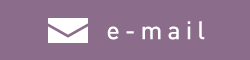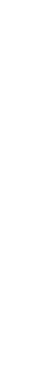建築と六曜
2023.06.26
こんにちは!
今回は建築と六曜の関係についてお話ししたいと思います。
六曜(ろくよう・りくよう)と聞くと、なんとなく「大安が良い」「仏滅が悪い」というイメージがありますが、具体的にはよく分からないという方も多いのではないでしょうか。
そもそも六曜は中国の宋の時代に考案された陰陽五行説に基づく六つの日のことです(当初は時刻占いとして1日を6つの時間帯に分けて考えられていました)。中国では武将が戦いを占うためにも使っていたようです。
鎌倉時代末期に日本へ伝承された際は曜日のように扱われていましたが、その後、日の吉凶へ割り当てられて現代まで使われてきました。六輝(ろっき)ともいわれています。
種類について、ひとつひとつご紹介致します。
◉先勝(せんしょう/さきがち)
「先んずれば勝つ」として、必要事はできるかぎり先回りして午前中に行うのが良いとされる日です。
◉友引(ともびき)
「凶事に友を引く」ということから勝負事が引き分けになる日でした。しかし意味が転じて友を引き寄せる日として幸せのお裾分けに適した日と考えられるようになりました。
◉先負(せんぷ/さきまけ)
「先んずれば即ち負ける」。先勝とは逆に、何をするにも午後におこなったほうが成功しやすい日とされています。
◉仏滅(ぶつめつ)
「仏も滅するような」大凶日。神事には悪い日ではないとされています。また、仏滅=物滅ととれることから、物事の終わり=始まりの日とも解釈されていて、何かを始めるには最適とも言われています。
◉大安(たいあん/だいあん)
「大いに安し」の意味があり、最も縁起の良い日です。お祝い事や願い事をするにも適していると言われています。
◉赤口(しゃっこう/せきぐち)
六曜を時間として使われていた時代、魔物がいる時刻にあてられていました。赤い口の鬼が災いをもたらす、という意味ですね。
「すべてが消滅する日」とされていますが、牛の刻(11時~13時)は鬼が休む時間のため、何かを行うならこの時間が良いとされています。
特に古くからある業界や神事・祭事と密接な業界では、今もなお日程の検討に活用されています。
ただし現代では昔ほど重視されることはなくなっており、建築業界でも六曜を順守するよりも計画や予算、工期、お客様のご要望や天気・気候などの実用的な要素が優先されることが一般的となっています。
また、建築においては六曜より「十二直(じゅうにちょく)」のほうが重視されることもあります。この「十二直」についてはまた次回お伝えしますね。
建築はただ機能やデザインだけでなく、そこに住まう方の文化や信念を反映したものでもあります。弊社ではお客様のご希望・ご要望をしっかりとお伺いしたうえで、施工計画には六曜を含む伝統的な要素を大切にしながら、理想の暮らしや住まいを追求しております。
今後も、建築にまつわる話や豆知識などのトピックをお届けしたいと思います。
引き続きよろしくお願いいたします。

BACK